IM
レポート
レポート
描かれたチャイナドレス ─ 藤島武二から梅原龍三郎まで
アーティゾン美術館 | 東京都
「チャイナドレス割引」も実施中
明治維新を経て、アジアでいち早く西欧化した日本。西欧化が進む一方で、中国への憧憬や愛着は絵画の中に生き続けました。日本人洋画家が描いた、中国服姿の女性像。少し珍しいテーマの企画展が、ブリヂストン美術館で開催中です。
0
(左から)藤島武二《鉸剪眉》鹿児島市立美術館蔵 / 藤島武二《女の横顔》ポーラ美術館蔵
(左から)藤島武二《唐様三部作》石橋財団石橋美術館蔵 / 藤島武二《匂い》東京国立近代美術館蔵
(左から)久米民十郎《支那の踊り》個人蔵 / 小林萬吾《銀屏の前》福富太郎コレクション資料室蔵
(左から)三岸好太郎《支那の少女》北海道立三岸好太郎美術館蔵 / 三岸好太郎《中国の女》メナード美術館蔵
(左から)児島虎次郎《お茶時》大原美術館蔵 / 児島虎次郎《中国の少女》大原美術館蔵
(左から)正宗得三郎《支那服》府中市美術館蔵 / 正宗得三郎《赤い支那服》府中市美術館蔵 / 小出楢重《周秋蘭立像》リーガロイヤルホテル蔵
(左から)児島虎次郎《花卓の少女》高梁市成羽美術館蔵 / 児島虎次郎《西湖の画舫》高梁市成羽美術館蔵
[清朝期の伝統旗袍 謝黎コレクション] 絵画の時代と同時期のチャイナドレスも参考出品されました
会場
| 会場 | |
| 会期 |
2014年4月26日(土)~2014年7月21日(月・祝)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00-18:00 (祝日を除く毎週金曜日は20:00まで) 【日時指定予約制】 入館までの待ち時間の緩和、より快適な鑑賞環境をご提供するために、1日を以下の入館時間枠に区切り、その時間枠内にご入館頂きます。 ①10:00-11:30 ②12:00-13:30 ③14:00-15:30 ④16:00-17:30 ⑤金曜日のみ 18:00-19:30(ただし祝日を除く) ※指定した時間枠内であれば、いつでもご入館頂けます。 ※入館後は閉館まで時間制限なくご鑑賞頂けます。入替制ではありません。 ※各時間枠の開始時刻直後は混雑が予想され、入館をお待ち頂く場合があります。 |
| 休館日 | 月曜日休館 ただし祝日は開館し、翌日休館 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-10-1 |
| 電話 | 03-5777-8600 |
| 公式サイト | http://www.bridgestone-museum.gr.jp |
| 料金 | 一般 800(600)円/シニア(65歳以上) 600(500)円/大学・高校生 500(400)円/中学生以下無料 ※()内は15名以上の団体料金 ※上記は、本展の料金となります。展覧会によって入館料は異なります。 ※シニアの方、学生の方は証明書が必要です。 ※障害者手帳をお持ちの方とご同伴者2名様まで半額となります。 |
| 展覧会詳細 | 「描かれたチャイナドレス─藤島武二から梅原龍三郎まで」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2026年1月9日
怒りと守護のかたち ─ 静嘉堂文庫美術館で「たたかう仏像」展が開催中
2026年1月9日
新宿からたどる日本近代美術 ― SOMPO美術館「モダンアートの街・新宿」
2026年1月9日
博物館学の原点を問う新刊 ― 『博物館学の原理 何のための博物館学』
ご招待券プレゼント
学芸員募集
歴史的建造物と庭園で働きたい方を募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【R8.4採用】金沢美術工芸大学 非常勤職員(美術館事務員)の募集について
[公立大学法人 金沢美術工芸大学]
石川県
杉並区立郷土博物館 学芸員募集
[杉並区立郷土博物館または杉並区立郷土博物館分館]
東京都
【パート★扶養内OK】ムラーボ!(子供向け体験型施設)案内スタッフ 募集!
[横浜市西区みなとみらい4丁目3-8(ムラーボ!)]
神奈川県
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


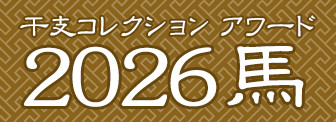

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)