IM
レポート
レポート
高野山金剛峯寺襖絵完成記念 千住博展 日本の美を極め、世界の美を拓く
そごう美術館(横浜駅東口 そごう横浜店 6階) | 神奈川県
奉納前に、展覧会でお披露目
1995年のヴェネツィア・ビエンナーレで東洋人として初めて名誉賞を受賞して以来、国内外で活躍を続けている画家・千住博(1958-)さん。世界遺産・高野山金剛峯寺に奉納される作品などを紹介する巡回展が、そごう美術館で開催中です。
0
《瀧図》2018 高野山金剛峯寺
《断崖図 #22》2016
(左から)《四季瀧図(秋)》1999 軽井沢千住博美術館 / 《四季瀧図(夏)》1999 軽井沢千住博美術館
《断崖図》2018 高野山金剛峯寺
《龍神Ⅰ、Ⅱ》2015 軽井沢千住博美術館
《湖畔初秋図》1993 軽井沢千住博美術館
(左から)《朝》1994 日本空港ビルデング株式会社 / 《水》1994 日本空港ビルデング株式会社
《終着駅》1985 軽井沢千住博美術館
(左から)《月響》2006 軽井沢千住博美術館 / 《遥か(青い鳥)》1980 軽井沢千住博美術館
| 会場 | |
| 会期 |
2019年3月2日(土)~4月14日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~20:00(入館は閉館の30分前まで) ※そごう横浜店の営業時間に準じる |
| 休館日 | そごう横浜店の休業日に準じる |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 |
| 電話 | 045-465-5515 |
| 公式サイト | https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/archives/19/senju_hiroshi/ |
| 料金 | 大人 1,300(1,100)円 / 大学・高校生 800(600)円 / 中学生以下 無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※障がい者手帳各種をお持ちの方および同伴者1名は無料 |
| 展覧会詳細 | 「高野山金剛峯寺 襖絵完成記念 千住 博展 ― 日本の美を極め、世界の美を拓く ―」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2026年1月9日
博物館学の原点を問う新刊 ― 『博物館学の原理 何のための博物館学』
2026年1月7日
京都の名家十二家が集結 ― 松屋銀座で「特別展 京都 十二の家」
2026年1月6日
たまごっち30周年 ─ 記念の展覧会が六本木ミュージアムで開幕へ
ご招待券プレゼント
学芸員募集
歴史的建造物と庭園で働きたい方を募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【R8.4採用】金沢美術工芸大学 非常勤職員(美術館事務員)の募集について
[公立大学法人 金沢美術工芸大学]
石川県
杉並区立郷土博物館 学芸員募集
[杉並区立郷土博物館または杉並区立郷土博物館分館]
東京都
【パート★扶養内OK】ムラーボ!(子供向け体験型施設)案内スタッフ 募集!
[横浜市西区みなとみらい4丁目3-8(ムラーボ!)]
神奈川県
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


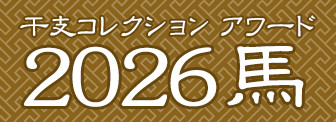

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)