IM
レポート
レポート
江戸の女装と男装
太田記念美術館 | 東京都
男女の入れ替え、自由自在
「LGBT」という言葉はありませんでしたが、江戸時代にも男装する女性や、女装する男性という「異性装」の文化がありました。祭礼において、歌舞伎において、そして絵の中の表現として…。男女の境界を自由に超えてきた浮世絵を紹介する展覧会が、太田記念美術館で開催中です。
0
(左から)菊川英山《青楼仁和嘉全盛遊》文化8~10年(1811~13)頃 個人蔵 / 落合芳幾《新吉原角街稲本楼ヨリ 仲之街仁和賀一覧之図》明治2年(1869)8月 国立音楽大学附属図書館蔵 竹内道敬文庫
楊洲周延《新吉原仁和賀の賑》明治21年(1888)8月 国立音楽大学附属図書館
(左から)歌川国貞《美人合 俄》文政12年(1829)頃 太田記念美術館 / 月岡芳年《風俗三十二相 にあいさう 弘化年間廓の芸者風俗》明治21年(1888)4月 太田記念美術館
歌川国芳《祭礼行列》天保15年(1844)頃 国立音楽大学附属図書館蔵 竹内道敬文庫
(左手前から)歌川広重《東海道五十三図会 四十四 四日市 諏訪明神祭礼》嘉永2~4年(1849~51)頃 太田記念美術館 / 歌川国貞(三代豊国)《江戸名所百人美女 山王御宮》安政4年(1857)11月 太田記念美術館
(左から)歌川国貞(三代豊国)《八代目市川団十郎の巫福寿宝子実ハ児雷也》嘉永5年(1852)7月 早稲田大学演劇博物館 / 歌川国貞(三代豊国)《『しらぬひ譚』》嘉永6年(1853)4月 個人蔵
(左から)歌川国貞《楽屋錦絵二編 十枚之内 五代目岩井半四郎》文化9年(1812)3月 個人蔵 / 歌川国貞《不二都久葉あいあい傘》天保2年(1831)頃 個人蔵
(左から)歌川国貞(三代豊国)《源氏見立八景之内 空蝉暮雪 から衣》安政5年(1858)8月 太田記念美術館 / 豊原国周《三代目沢村田之助(死絵)》明治11年(1878)7月 太田記念美術館
(左から)鳥文斎栄之《見立五人の茶屋女》寛政5年(1793)頃 太田記念美術館 / 喜多川歌麿《高名美人見たて忠臣蔵 弐たんめ》寛政6~7年(1794~95)頃 太田記念美術館
| 会場 | |
| 会期 |
2018年3月2日(金)~3月25日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:30~17:30(入館17:00まで) |
| 休館日 | 3月5、12、19日は休館 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-10-10 |
| 電話 | 03-5777-8600 |
| 公式サイト | http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/ |
| 料金 | 一般 700円 大高生 500円 中学生以下 無料 |
| 展覧会詳細 | 「江戸の女装と男装」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年12月15日
古伊万里の「いきもの」80点が集合 ― 戸栗美術館「古伊万里 いきもの図会展」が1月開催
2025年12月15日
福山潤「世界観を存分に楽しんで」 ― 「アニメ天官賜福展」横浜で開幕
2025年12月14日
戦後美術史に新たな光 ─ 東京国立近代美術館で「アンチ・アクション」展
2025年12月12日
芽吹く生命をアートで体感 ─ ポーラ美術館 「SPRING わきあがる鼓動」
2025年12月11日
写真で捉える地球の現在 ─ プリピクテ「STORM 嵐」開催
ご招待券プレゼント
学芸員募集
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!
[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]
東京都
長野県立美術館 学芸員募集中!
[長野県立美術館]
長野県
令和7年度採用 契約職員募集
[静岡科学館、清水文化会館、生涯学習センター(予定)]
静岡県
江戸東京博物館 接客案内責任者募集
[江戸東京博物館]
東京都
展覧会ランキング
3
TOKYO NODE | 東京都
Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』
開催中[あと24日]
2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)



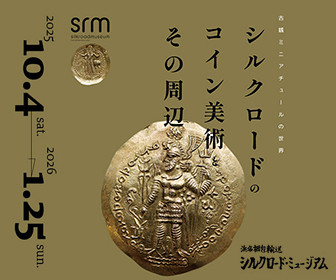
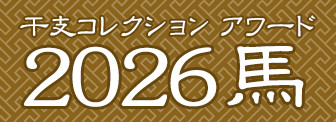

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)