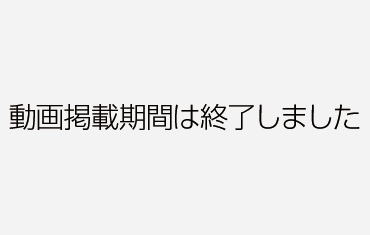IM
レポート
レポート
花ひらく琳派 絵画とやきものでたどる装飾美の系譜
サンリツ服部美術館 | 長野県
偶然から生まれた、「二つと無い」逸品
「琳派400年」の今年は各地で続々と琳派展が開かれていますが、長野・諏訪市のサンリツ服部美術館でも琳派の絵画とやきものの優品を紹介する企画展が開幕。琳派の祖・本阿弥光悦による国宝《白楽茶碗 銘 不二山》も特別出品されています。
0
本阿弥光悦 国宝《白楽茶碗 銘 不二山》(手前)
俵屋宗達下絵・本阿弥光悦書《四季草花下絵新古今集和歌色紙帖》
(手前)《織部大徳利》
(左手前)「乾山」印《色絵絵替土器皿》 / (右奥)「乾山」印《錆絵槍梅文鉢》
酒井抱一《紅白梅図屏風 右隻 白梅》
《鼠志野竹図向付》
《織部手鉢》
| 会場 | |
| 会期 |
2015年7月18日(土)~11月15日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 9:30~16:30 |
| 休館日 | 月曜日休館 ただし祝日の場合は開館 8月は無休 |
| 住所 | 長野県諏訪市湖岸通り2-1-1 |
| 電話 | 0266-57-3311 |
| 公式サイト | http://www.sunritz-hattori-museum.or.jp/ |
| 料金 | 大人 800(700)円/小中学生 400(350)円 ※( )は団体20名様以上の料金 |
| 展覧会詳細 | 「花ひらく琳派 絵画とやきものでたどる装飾美の系譜 」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年7月5日
伝統と革新の融合 ― 愛知県美術館「近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳」
2025年7月4日
写真が紐解くフジタの真髄 ― 東京ステーションギャラリー「藤田嗣治 絵画と写真」
2025年7月4日
色と形の魔法使い ― ヒカリエホール「レオ・レオーニの絵本づくり展」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
あべのハルカス美術館 学芸員募集
[あべのハルカス美術館]
大阪府
北海道標津町文化財担当職員募集
[標津町ポー川史跡自然公園]
北海道
人と防災未来センター 震災資料専門員(会計年度雇用職員)の募集
[人と防災未来センター 資料室]
兵庫県
アーツ前橋 学芸員(正規職員)募集
[アーツ前橋]
群馬県
【R8.4.1採用】世田谷区Ⅰ類「学芸研究」(学芸員・建造物担当)募集
[世田谷区]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)