読者
レポート
レポート
世田谷美術館コレクション選 わたしたちは生きている! セタビの森の動物たち
世田谷美術館 | 東京都
| 会場 | 世田谷美術館 |
| 会期 |
2023年2月18日(土)〜4月9日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~18:00(入場は17:30まで) |
| 休館日 | 毎週月曜日 |
| 住所 | 〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 |
| 電話 | 03-3415-6011 (代表)
03-3415-6011
(代表)
|
| 公式サイト | https://www.setagayaartmuseum.or.jp/ |
| 展覧会詳細 | 「世田谷美術館コレクション選 わたしたちは生きている! セタビの森の動物たち」 詳細情報 |
0
読者レポーターのご紹介
さつま瑠璃
美術を主軸とする記者/編集者/エッセイスト。“やさしい言葉でartをもっと楽しく身近に” をコンセプトに、Blog「さつまがゆく」やSNSでアート情報を発信しています。
おすすめレポート
ニュース
2026年1月16日
海外所蔵浮世絵が一堂に ─ 千葉市美術館で「ロックフェラー・コレクション花鳥版画展」
2026年1月16日
鹿子木孟郎の写実絵画を総覧 ― 泉屋博古館東京
2026年1月15日
「TERRADA ART AWARD 2025」審査員賞が決定
2026年1月15日
制作過程を多彩な資料で紹介 ― 「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」
2026年1月14日
20世紀日本の理想郷を描く ― 「美しいユートピア」展、パナソニック汐留美術館で開催
ご招待券プレゼント
学芸員募集
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
横浜みなと博物館 博物館業務アルバイト募集!
[横浜みなと博物館]
神奈川県
川崎市岡本太郎美術館 会計年度任用職員(資料デジタル化業務・普及企画業務)の募集
[川崎市岡本太郎美術館]
神奈川県
福島県教育委員会 任期付職員(学芸員(考古学))募集
[福島県教育庁文化財課南相馬市駐在]
福島県
独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 文化財情報資料部 有期雇用職員(近・現代視覚芸術研究室 研究補佐員)募集
[東京文化財研究所文化財情報資料部 近・現代視覚芸術研究室(東京都台東区上野公園13-43)]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)














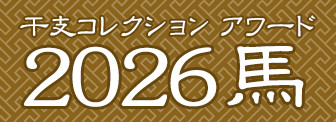

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)