IM
レポート
レポート
黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部 ―美濃の茶陶
サントリー美術館 | 東京都
黄‘瀬戸’なのに、美濃?
茶の湯が栄えた安土桃山時代。美濃国(岐阜県東濃地域)でつくられたやきものは、独創的な意匠で人々の心を捉え、おおいに珍重されました。その造形的な魅力と、近代以降の美濃焼復興を紹介する展覧会が、サントリー美術館で開催中です。
0
(左手前から)重要文化財《織部松皮菱形手鉢》桃山時代 17世紀 北村美術館 / 《瀬戸黒筒茶碗 銘 宗潮黒》桃山時代 16~17世紀 公益財団法人香雪美術館
(左から)《黄銅立鼓花入》明時代 15世紀 野村美術館[展示期間:9/4~9/30] / 《黄瀬戸立鼓花入》桃山時代 16~17世紀 サントリー美術館
《志野草花文鉢》桃山時代 16~17世紀 サントリー美術館
(左から)《織部耳付花入》桃山時代 17世紀 個人蔵 / 重要文化財《志野松籬図水指》桃山時代 16~17世紀 公益財団法人香雪美術館
(左手前から)《織部舟形向付》桃山時代 17世紀 個人蔵 / 《織部切落向付》桃山時代 17世紀 MIHO MUSEUM
《織部四方蓋物》桃山時代 17世紀 サントリー美術館
(左奥から)《志野茶碗 銘 氷柱》加藤唐九郎 昭和5年(1930) 唐九郎陶芸記念館 / 《瀬戸黒茶碗 銘 初雪》加藤唐九郎 昭和21年(1946) 唐九郎陶芸記念館
(左奥から)《志野茶碗 銘 鯨帯》加藤唐九郎 昭和44年(1969) 愛知県陶磁美術館(川崎音三氏寄贈) / 《黄瀬戸茶碗》加藤唐九郎 昭和57年(1982) 唐九郎陶芸記念館 / 《茜志野茶碗》加藤唐九郎 昭和60年(1985) 唐九郎陶芸記念館
(左手前から)重要文化財《鼠志野茶碗 銘 峯紅葉》桃山時代 16~17世紀 五島美術館[展示期間:9/4~10/7] / 《志野茶碗 銘 朝日影》桃山時代 16~17世紀 公益財団法人香雪美術館 / 《志野茶碗 銘 橋姫》桃山時代 16~17世紀 東京国立博物館
| 会場 | |
| 会期 |
2019年9月4日(水)~11月10日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~18:00 |
| 休館日 | 火曜日(ただし、11月5日は18時まで開館) |
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3F |
| 電話 | 03-3479-8600 |
| 公式サイト | https://www.suntory.co.jp/sma/ |
| 料金 | 一般 1,300(1,100)円 / 大学・高校生 1,000(800)円 / 中学生以下 無料 ※20名以上の団体は100円割引 ※( )内は前売り料金。前売券販売は、サントリー美術館受付、サントリー美術館公式オンラインチケット、チケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケット、イープラスにて取扱(各種プレイガイドは一般券のみ販売) ※前売券の販売は2019年6月26日(水)~9月 3日(火)。サントリー美術館受付での前売券販売(一般、大学・高校生)は6月26日(水)~8月18日(日)の開館日に限る。 |
| 展覧会詳細 | 「「黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部 ―美濃の茶陶」展」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年12月25日
新選組への商品代金の受領記録などが初公開 ― 高島屋史料館「タカシマヤ クロニクル」展
2025年12月24日
人気青春漫画『スキップとローファー』の展覧会がサンシャインで開催
2025年12月22日
博物館の持続可能なコレクション管理を考える ― 無料シンポジウムが1/24に開催
2025年12月18日
日高のり子も感動、貴重な原画がずらり ─ 画業55周年「あだち充展」
2025年12月18日
カプコンの制作世界を一望 ─ CREATIVE MUSEUM TOKYOで「大カプコン展」
ご招待券プレゼント
織田コレクション ハンス・ウェグナー展
応募する
つぐ minä perhonen
応募する
学芸員募集
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!
[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]
東京都
国立国際美術館 ボランティア募集中!
[国立国際美術館]
大阪府
川崎市市民ミュージアム 学芸員(美術館学芸員・教育普及学芸員)募集
[川崎市市民ミュージアム]
神奈川県
和歌山市職員 学芸員[日本近世史]の募集
[和歌山市役所(和歌山城整備企画課、和歌山市立博物館等)]
和歌山県
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


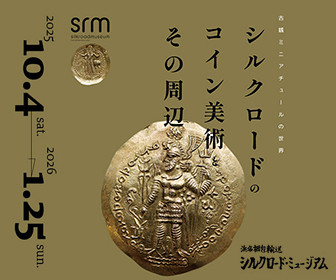
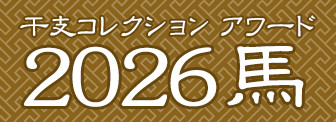

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)