IM
レポート
レポート
エジプトに魅せられた昭和の人々 ― 古代オリエント博物館「やっぱりエジプトが好き♡」(レポート)
古代オリエント博物館 | 東京都
昭和30〜40年代に日本で広まった“エジプト柄”ブームを、生活資料で紹介
ツタンカーメン展より前。昭和の日本人はなぜ古代エジプトに憧れたのか?
北名古屋市歴史民俗資料館(昭和日常博物館)の所蔵資料を中心にした構成
0
古代オリエント博物館「やっぱりエジプトが好き♡」会場風景
古代オリエント博物館「やっぱりエジプトが好き♡」会場風景
| 会場 | 古代オリエント博物館 |
| 会期 |
2025年9月27日(土)〜11月24日(月)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) ※10/2と11/21は20:00まで開館します(最終入館19:30) |
| 休館日 | 会期中無休 |
| 住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ文化会館ビル7階 |
| 電話 | 03-3989-3491 |
| 公式サイト | https://aom-tokyo.com/ |
| 料金 | 一般 1000円、大高生 800円、中小生600円 ※20名以上の団体割引、障害者割引あり ※「障害者手帳」をお持ちの方は半額割引(付き添いの方は1名入館無料) |
| 展覧会詳細 | 「やっぱりエジプトが好き💛 ―昭和のニッポンと古代のエジプト―」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2026年1月20日
装い新たに日本を読み解く、東洋文庫ミュージアムがリニューアルオープン
2026年1月19日
名刀と大名文化を紹介 ─ 特別展「百万石!加賀前田家」、東博で4月に開催
2026年1月16日
海外所蔵浮世絵が一堂に ─ 千葉市美術館で「ロックフェラー・コレクション花鳥版画展」
2026年1月16日
鹿子木孟郎の写実絵画を総覧 ― 泉屋博古館東京
ご招待券プレゼント
学芸員募集
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー)など]
東京都
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
茨城県近代美術館 学芸補助員(普及担当)及び展示解説員募集
[茨城県近代美術館]
茨城県
国⽴国際美術館 研究補佐員(教育普及室)募集
[国立国際美術館]
大阪府
横浜みなと博物館 博物館業務アルバイト募集!
[横浜みなと博物館]
神奈川県
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


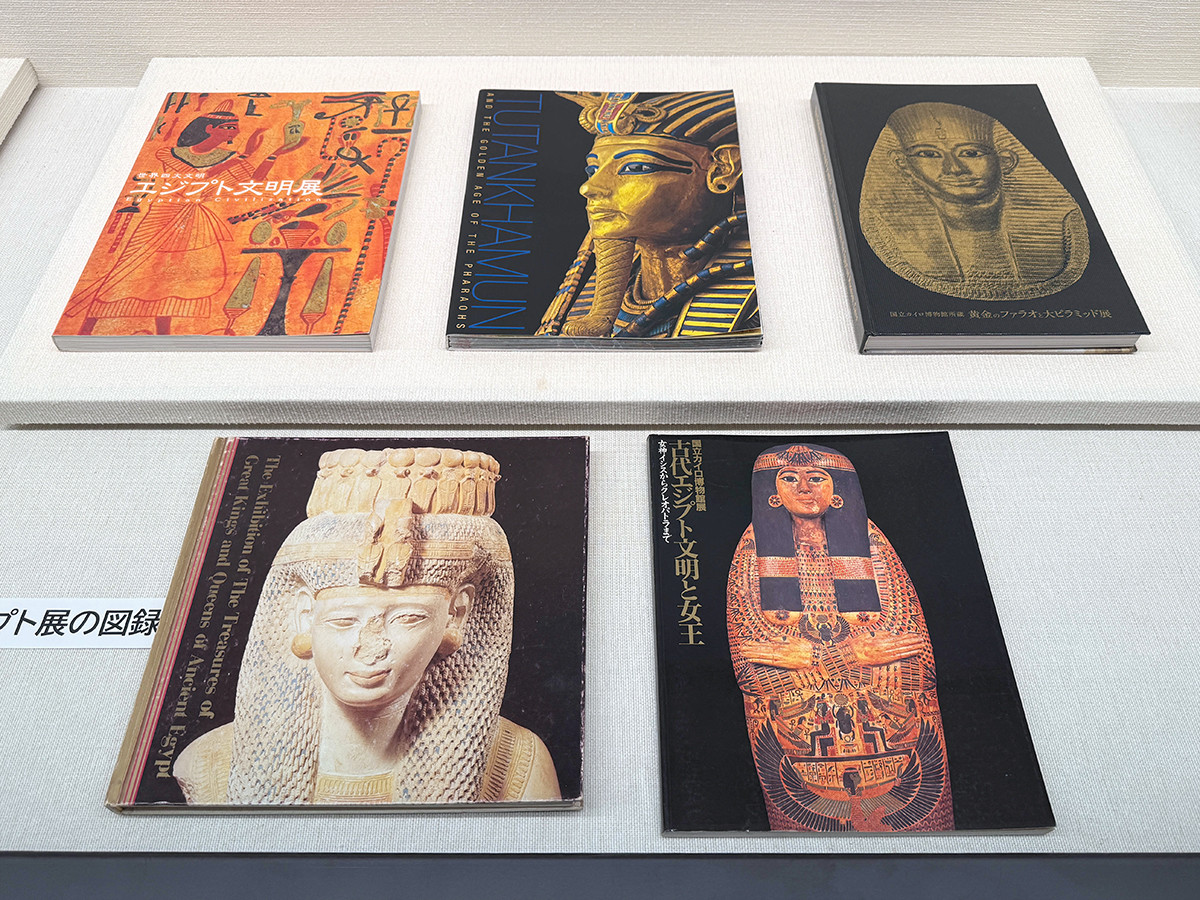

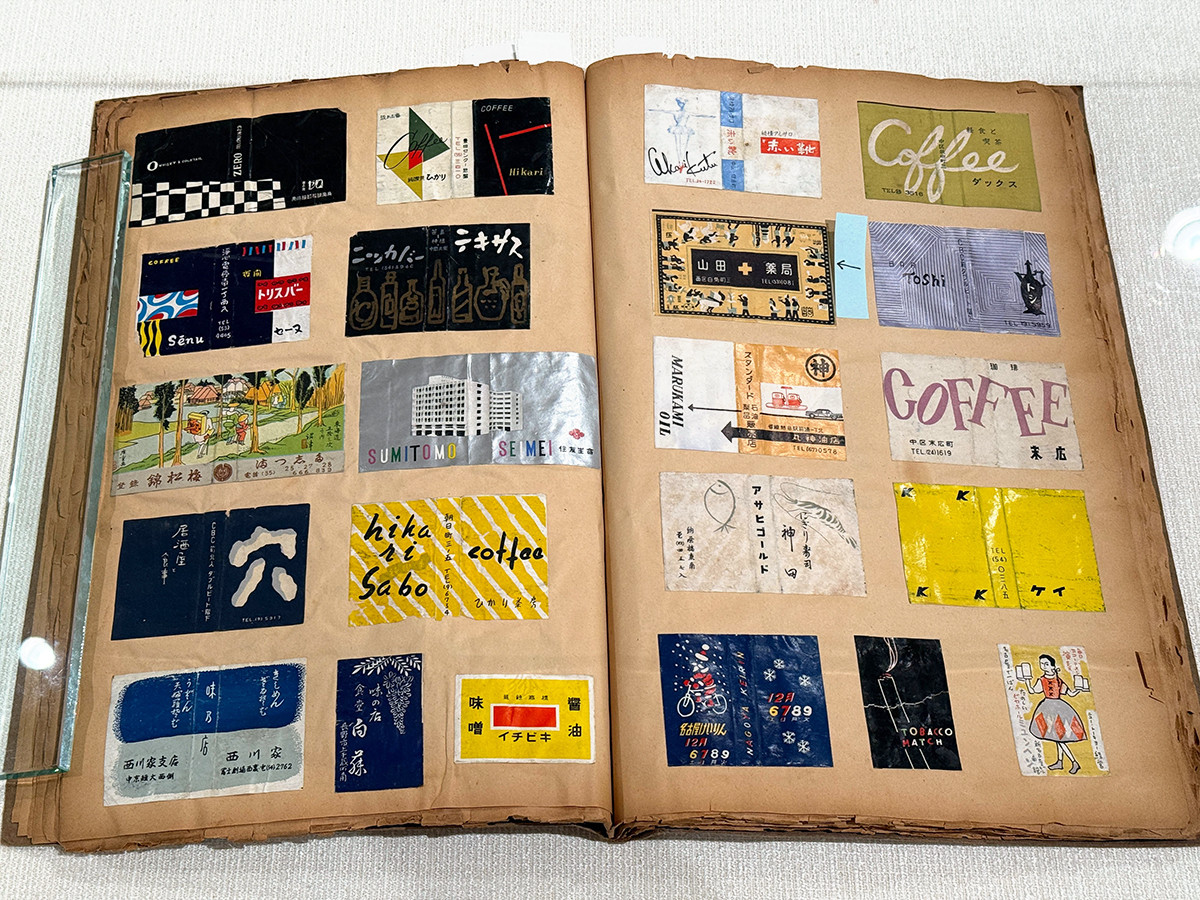

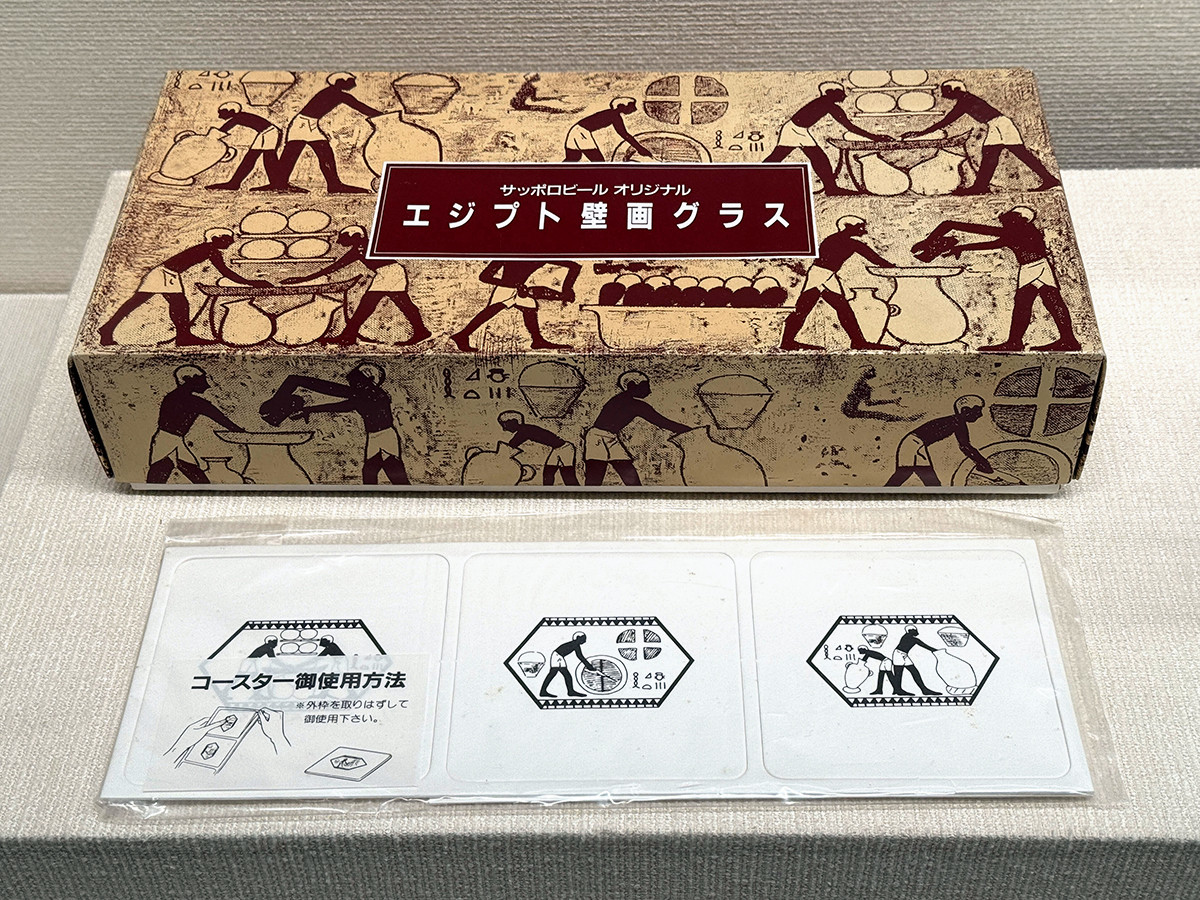
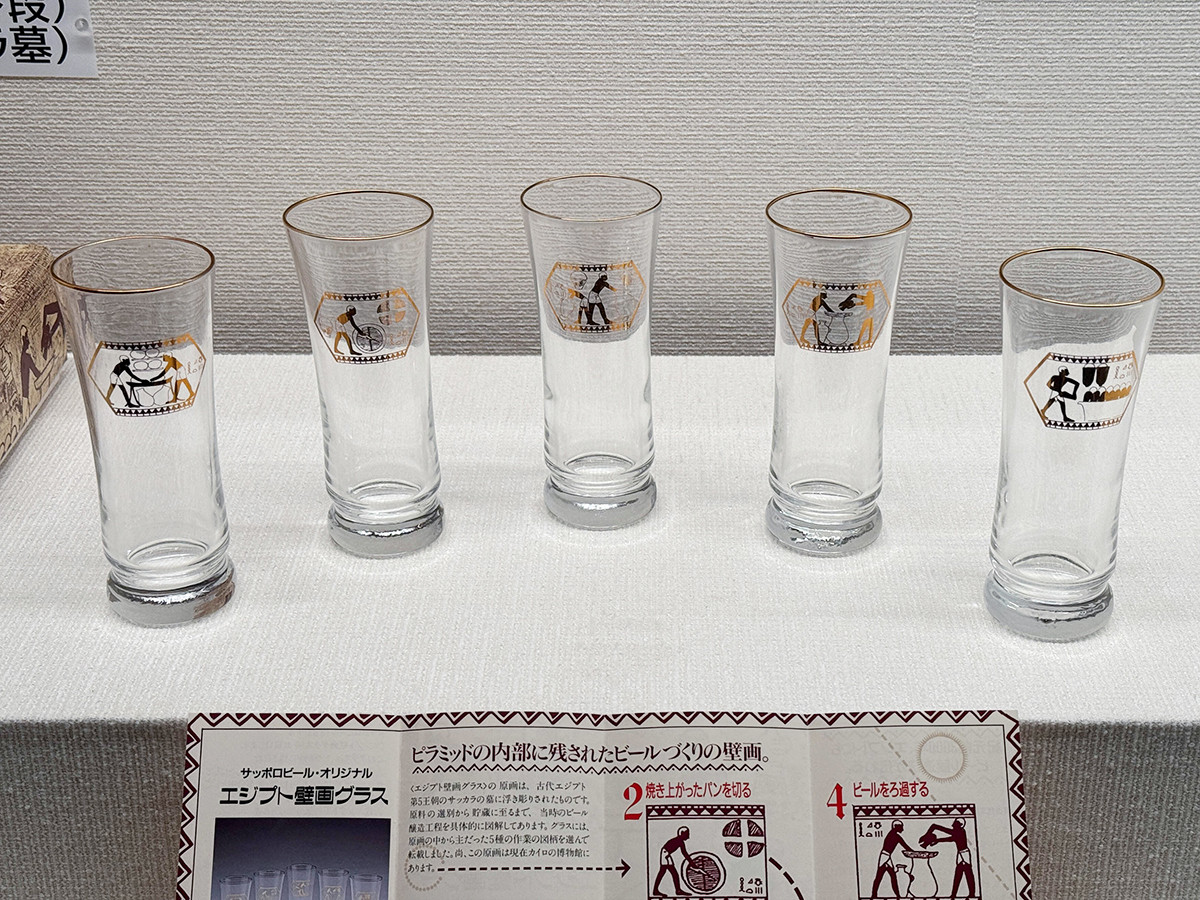
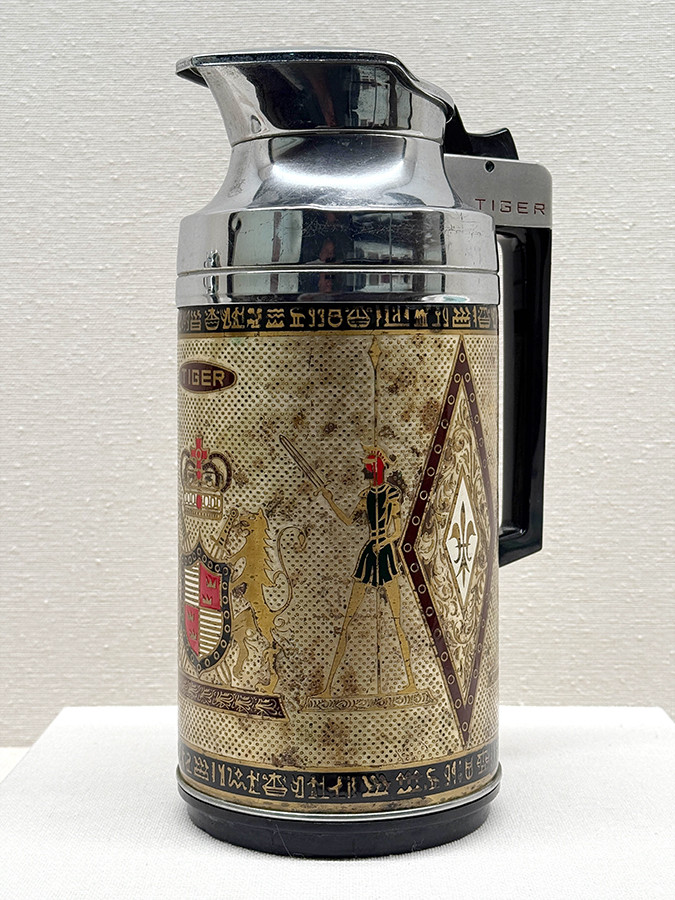

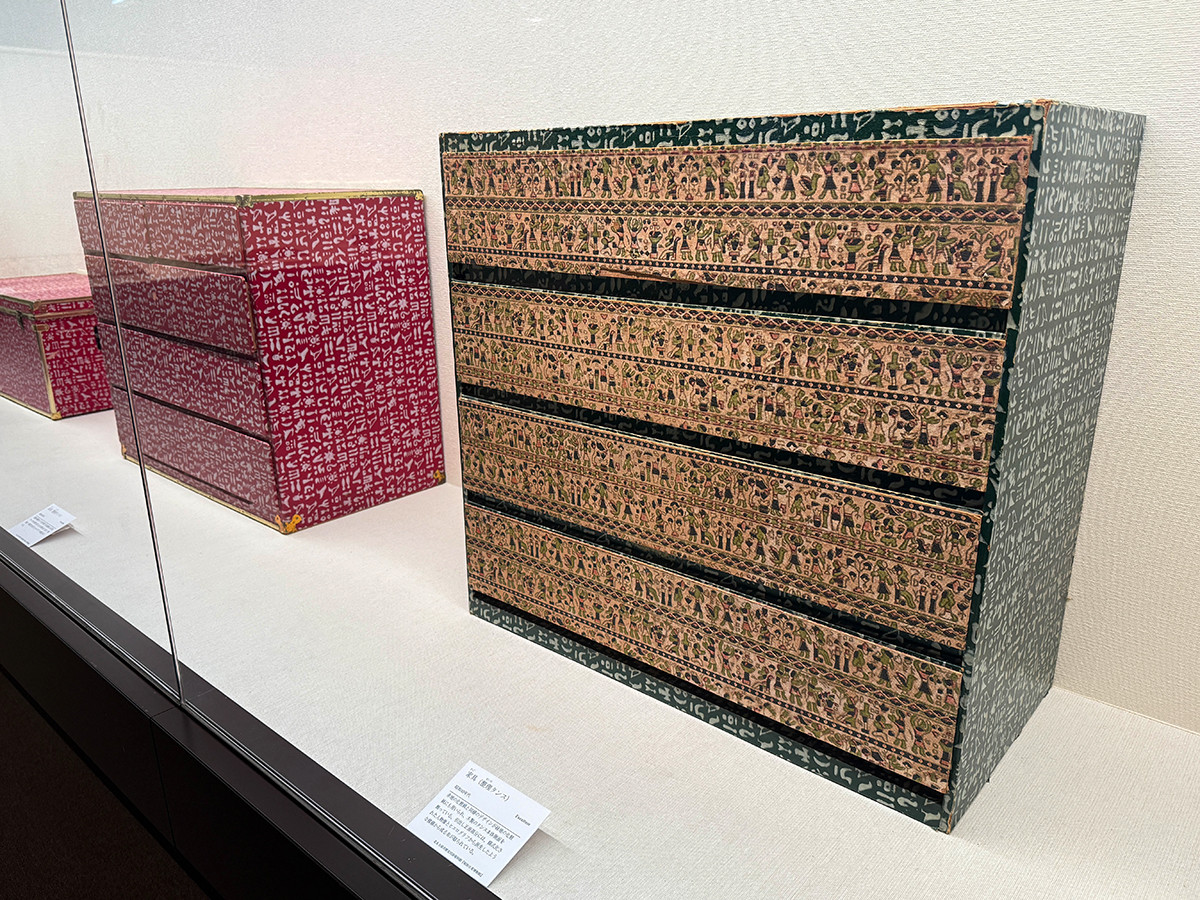
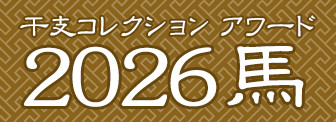

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)