IM
レポート
レポート
芸術と民族の魂が共鳴 ― 「岡本太郎と太陽の塔―万国博に賭けたもの」(取材レポート)
川崎市岡本太郎美術館 | 神奈川県
1970年大阪万博のレガシー「太陽の塔」に込めた岡本太郎の思想を読み解く
制作記録写真や民族資料などを展示しながら太陽の塔の内外を多角的に体感
「人間の誇りと歓びを爆発させる祭り」が万博。岡本の思想的背景を深堀り
2
| 会場 | 川崎市岡本太郎美術館 |
| 会期 |
2025年4月26日(土)〜7月6日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 9:30-17:00(入館16:30まで) |
| 休館日 | 月曜日(4月28日、5月5日を除く)、5月7日(水)、5月8日(木) |
| 住所 | 〒214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形7-1-5 生田緑地内 |
| 電話 | 044-900-9898 |
| 料金 | 一般900(720)円、高・大学生・65歳以上700(560)円 ※( )内は20名以上の団体料金 ※中学生以下は無料 |
| 展覧会詳細 | 「企画展「岡本太郎と太陽の塔―万国博に賭けたもの」」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年12月18日
日高のり子も感動、貴重な原画がずらり ─ 画業55周年「あだち充展」
2025年12月18日
カプコンの制作世界を一望 ─ CREATIVE MUSEUM TOKYOで「大カプコン展」
2025年12月18日
トヨタが手がける没入型ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA」が横浜に誕生
2025年12月15日
古伊万里の「いきもの」80点が集合 ― 戸栗美術館「古伊万里 いきもの図会展」が1月開催
2025年12月15日
福山潤「世界観を存分に楽しんで」 ― 「アニメ天官賜福展」横浜で開幕
ご招待券プレゼント
学芸員募集
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!
[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]
東京都
京都産業大学・嘱託職員募集
[京都産業大学]
京都府
酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館)アルバイト募集
[公益財団法人白鹿記念酒造博物館]
兵庫県
山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 学芸員募集
[山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館]
鳥取県
展覧会ランキング
3
TOKYO NODE | 東京都
Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』
開催中[あと19日]
2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)







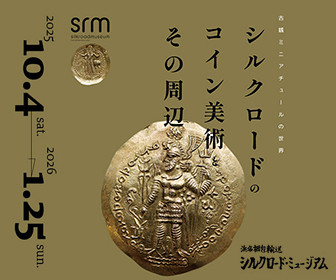
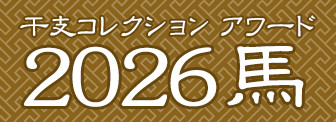

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)