IM
レポート
レポート
メスキータ
東京ステーションギャラリー | 東京都
エッシャーの師、日本初の大回顧展
19世紀から20世紀にかけて活躍したオランダのアーティスト、サミュエル・イェスルン・デ・メスキータ(1868-1944)。エッシャーに大きな影響を与えましたが、その最期は悲劇的でした。日本で初めての回顧展が東京ステーションギャラリーで開催中です。
0
(左から)《マントを着たヤープ》 1913 / 《ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像》 1922
(左から)《髭に手をやる自画像》 1917 / 《パイプをくわえた自画像》 1900
(左から)《ドーラ》 1895頃 / 《ベッティ・ロペス・デ・レアオ・ラグーナの肖像》 1908
(左から)《喜び(裸婦)》 1914 / 《悲しみ(裸婦)》 1914
(左端から時計回りで)《ユリ》第1ステート(全5ステートのうち) / 《ユリ》第2ステート(全5ステートのうち) / 《ユリ》第4ステート(全5ステートのうち) / 《ユリ》第3ステート(全5ステートのうち) すべて 1916-17
(左から)《鹿》第10ステート(全10ステートのうち) / 《鹿》第9ステート(全10ステートのうち) ともに 1925
(左から)《ファンタジー:キッパーの男》 1905頃 / 《ファンタジー:紙片を持つ女(ルネに)》 1925
(左から)《ファンタジー:さまざまな人々(黒い背景)》 1921 / 《ファンタジー:三人の人物(青い顔)》 1922
(左奥から)《『ウェンディンゲン』第10巻10号 [特集:ロシア演劇]》 1930 / 《『ウェンディンゲン』第1巻10号 [特集:建築]》 1918
| 会場 | |
| 会期 |
2019年6月29日(土)~8月18日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~18:00 ※金曜日は20:00まで ※入館は閉館の30分前まで |
| 休館日 | 月曜日(7月15日、8月12日は開館)、7月16日(火) |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅 丸の内北口 改札前 |
| 電話 | 03-3212-2485 |
| 公式サイト | http://www.ejrcf.or.jp/gallery/ |
| 料金 | 一般 1,100(900)円 / 高校・大学生 900(700)円 / 中学生以下 無料 ※( )内は前売料金(4/27~6/28販売) ※20名以上の団体は、一般 800円、高校・大学生 600円 ※障がい者手帳等持参の方は100円引き(介添者1名は無料) ※前売券販売場所は、ローソンチケット(Lコード=33345)、イープラス、CNプレイガイド、セブンチケットにて販売(6/28まで)。美術館受付での販売は6/16までの開館日(閉館30分前まで)に限ります。 |
| 展覧会詳細 | 「メスキータ展」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年12月22日
博物館の持続可能なコレクション管理を考える ― 無料シンポジウムが1/24に開催
2025年12月18日
日高のり子も感動、貴重な原画がずらり ─ 画業55周年「あだち充展」
2025年12月18日
カプコンの制作世界を一望 ─ CREATIVE MUSEUM TOKYOで「大カプコン展」
2025年12月18日
トヨタが手がける没入型ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA」が横浜に誕生
2025年12月15日
古伊万里の「いきもの」80点が集合 ― 戸栗美術館「古伊万里 いきもの図会展」が1月開催
ご招待券プレゼント
学芸員募集
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!
[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]
東京都
国立科学博物館 事務補佐員(短時間勤務有期雇用職員)募集案内【上野地区】
[独立行政法人国立科学博物館【上野地区】]
東京都
【国立科学博物館】事務補佐員(有期雇用職員)募集案内【上野地区】
[独立行政法人国立科学博物館 上野地区]
東京都
京都産業大学・嘱託職員募集
[京都産業大学]
京都府
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


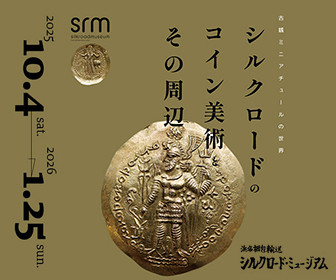
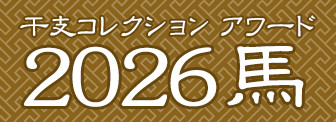

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)