IM
レポート
レポート
企画展示「ニッポンおみやげ博物誌」
国立歴史民俗博物館 | 千葉県
「おみやげ」から見るニッポン文化!
皆さんは「おみやげ」と聞くと、何を思い浮かべますか? 旅先のキーホルダー、人に配るためのご当地お菓子…。さまざまな「おみやげ」から日本の贈答文化を見直す展覧会が、国立歴史民俗博物館で開催中です。
0
4章「旅の文化の多様化とおみやげの展開」
(上から)《東都名所・金龍山之図》歌川広重画 佐野屋喜兵衛版 天保年間(1830~44)末期 国立歴史民俗博物館蔵 / 《東都名所・芝神明境内》歌川広重画 佐野屋喜兵衛版 天保年間(1830~44)前期 国立歴史民俗博物館蔵 / 《江戸買物独案内》大坂・中川芳山堂 1824(文政7)年 国立歴史民俗博物館蔵
3章「現代におけるおみやげの諸相」
3章「現代におけるおみやげの諸相」
(左上から)《黄鮒》栃木県 2018(平成30)年 個人蔵 / 《赤べこ》福島県 1960~80年代 国立歴史民俗博物館蔵 / 《姫だるま》愛媛県 1960~80年代 国立歴史民俗博物館蔵 / 《越前竹人形》福井県 1970~90年代 国立歴史民俗博物館蔵 / 《土人形 おわら土鈴》富山県 1960~80年代 国立歴史民俗博物館蔵
(左奥から)《屋久杉 飾り壺》屋久杉岳南 作:日高英世 / 《UKOUKU 輪唱》作:貝澤徹 いずれも2011(平成23)年 国立歴史民俗博物館蔵
(左上から)《クワガタ》東南アジア 1996(平成8)年 個人蔵 / 《タイマイ風の小物入れ》ベトナム 1990年代 個人蔵 / 《タイマイ》八丈島 1960年代 千葉県立中央博物館蔵
(左から)《スクラップブック 入場券その他》1914(大正3)年 国立歴史民俗博物館蔵 / 《西国三十三所名所図会》1848(嘉永元)年序 国立歴史民俗博物館蔵
(左から)《各種おみやげ、切符、栞の額装》戦後 千葉県立中央博物館蔵 / 《弁当の包装紙、その他の額装》戦後 千葉県立中央博物館蔵
| 会場 | |
| 会期 |
2018年7月10日(火)~9月17日(月・祝)
会期終了
|
| 開館時間 | 9:30~17:00(入館は16:30まで) (3~9月) 9:30~16:30(入館は16:00まで) (10~2月) |
| 休館日 | 月曜日(月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館) ※ただし、8月13日は開館 |
| 住所 | 千葉県佐倉市城内町117番地 |
| 電話 | 03-5777-8600(ハローダイヤル)
03-5777-8600
(ハローダイヤル)
|
| 公式サイト | https://www.rekihaku.ac.jp |
| 料金 | 一般 830(560)円 / 高校生・大学生 450(250)円 / 小・中学生 無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※総合展示もあわせてご覧になれます。 ※毎週土曜日は高校生は入館無料です。 ※高校生及び大学生の方は、学生証等を提示してください。(専門学校生など高校生及び大学生に相当する生徒、学生も同様です) ※障がい者手帳等保持者は手帳提示により、介護者と共に入館が無料です。 |
| 展覧会詳細 | 「企画展示「ニッポンおみやげ博物誌」」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年12月26日
「昭和の春信」を総覧 ― あべのハルカス美術館で「密やかな美 小村雪岱のすべて」
2025年12月25日
新選組への商品代金の受領記録などが初公開 ― 高島屋史料館「タカシマヤ クロニクル」展
2025年12月24日
人気青春漫画『スキップとローファー』の展覧会がサンシャインで開催
2025年12月22日
博物館の持続可能なコレクション管理を考える ― 無料シンポジウムが1/24に開催
2025年12月18日
日高のり子も感動、貴重な原画がずらり ─ 画業55周年「あだち充展」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
歴史的建造物と庭園で働きたい方を募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
ほまれあ(三条市歴史民俗産業資料館別館)学芸員募集
[ほまれあ(三条市歴史民俗産業資料館別館)]
新潟県
KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2026 サポートスタッフ募集(ボランティア)
[京都文化博物館 別館、誉田屋源兵衛 竹院の間、京都市京セラ美術館 別本館 南回廊2階、Ygion、ASPHODEL、嶋臺ギャラリー、出町桝形商店街など [京都府]]
京都府
2026.4.1採用 国立新美術館 総務課研究補佐員(広報室)公募(2026年2月2日正午締切)
[国立新美術館]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


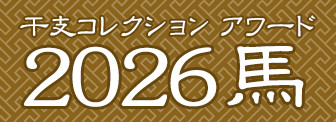

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)