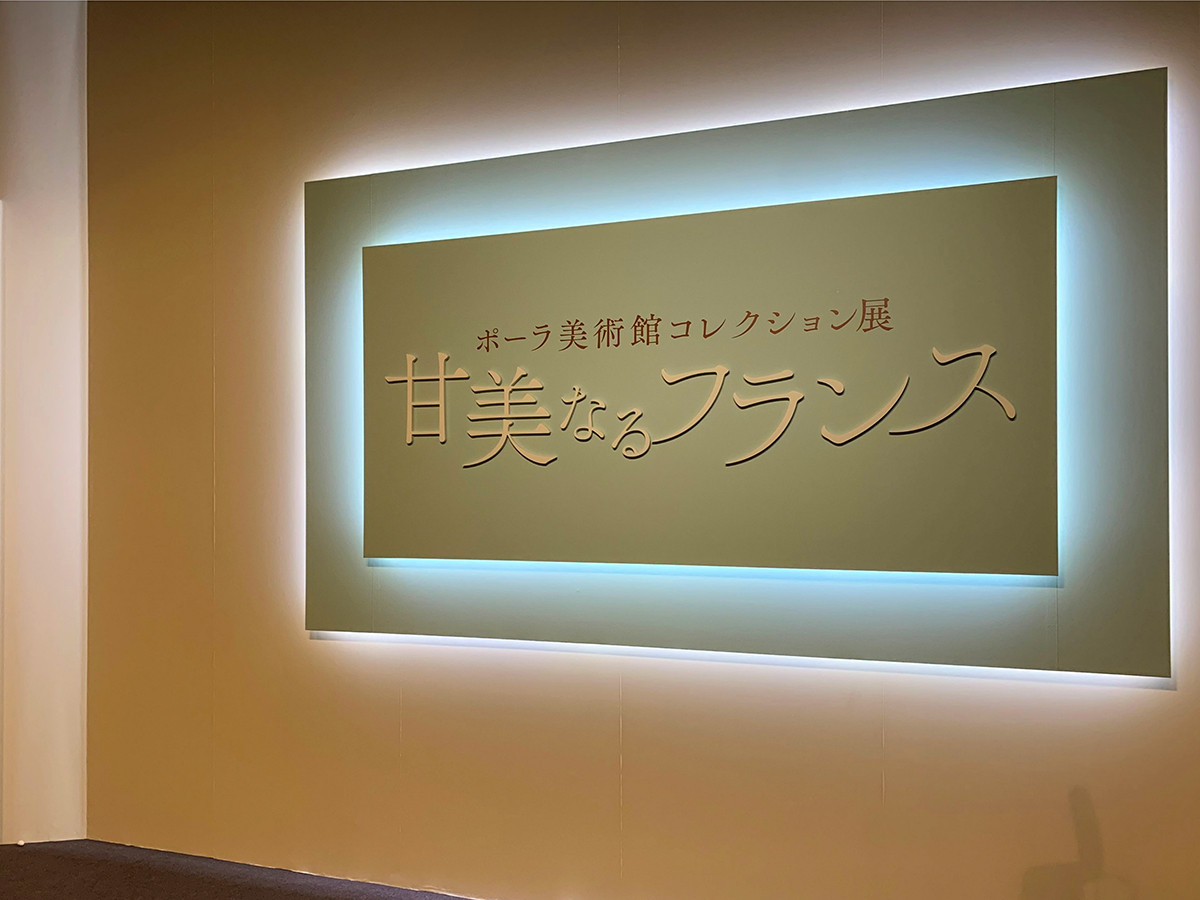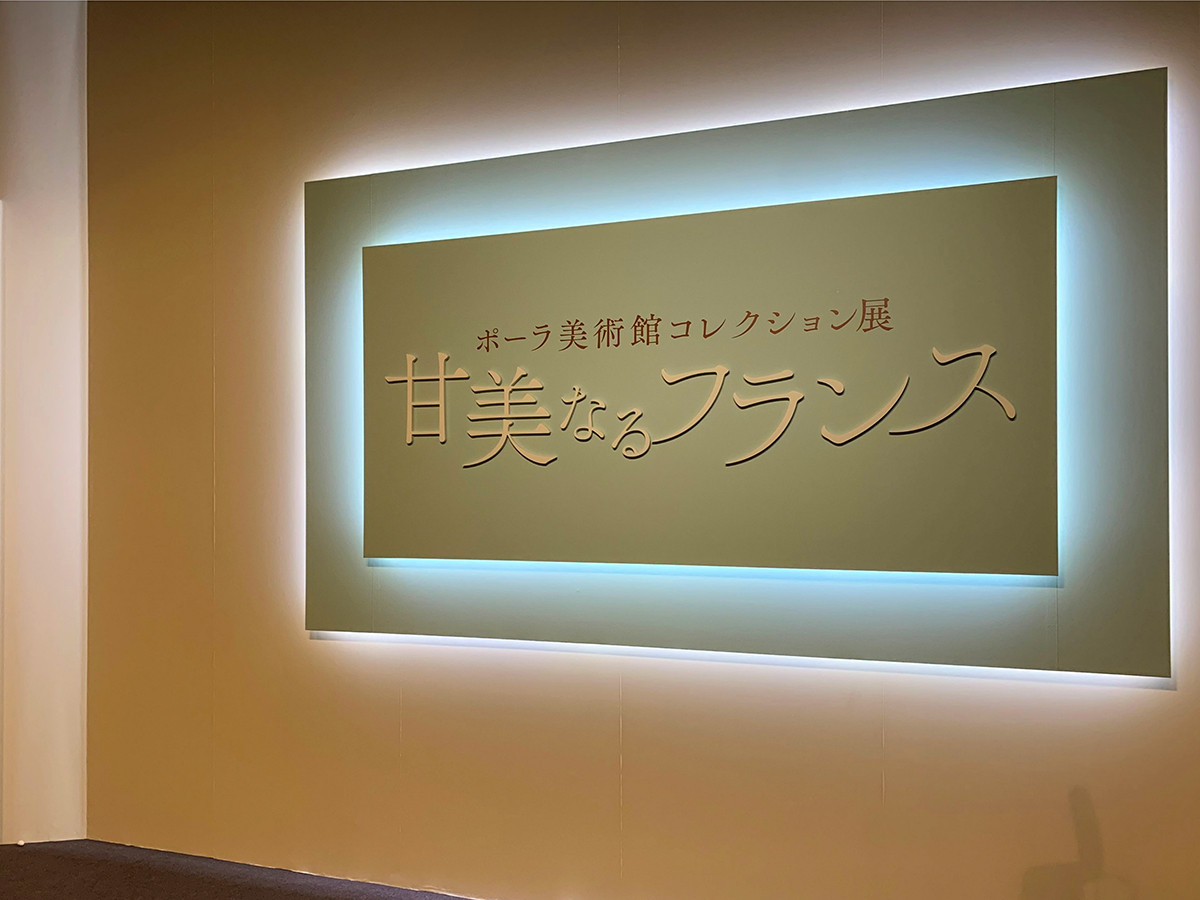
Bunkamuraザ・ミュージアム『ポーラ美術館コレクション展 ~甘美なるフランス~』エントランス
箱根の森に調和するように建つポーラ美術館は、遊歩道の散歩や屋外彫刻の鑑賞も楽しい美術館です。西洋絵画コレクションでもとても有名です。
一方、Bunkamuraザ・ミュージアムは喧騒の都会にあって、訪れる人をオアシスのように迎える美術館。テーマ性や先見性、話題性のある展覧会が人気です。
展覧会の背景にある「女性像」「パリ」「旅」という3つのテーマにも惹かれ、見学に行ってきました。
時代を映す女性像

ピエール・オーギュスト・ルノワール「髪かざり」(1888年),ウェブスター社「銀製化粧セット」(1900-1905)
第1章は「都市と自然」。本展覧会では、ポーラ美術館が収蔵する宝石のような化粧道具が、絵画に添えられるように展示されています。ふと、描かれている女性の部屋を訪ねているような気持ちになり、心は19世紀のパリへ。
「レースの帽子の少女」とアールヌーヴォー時代の香水瓶

ピエール・オーギュスト・ルノワール「レースの帽子の少女」(1891年),「エナメル金彩バラ文香水瓶(19世紀後半)
誰もが優しい気持ちに包まれるルノアールの「レースの帽子の少女」。その傍らには金彩と薔薇模様が施された香水瓶が置かれていました。清楚な少女の夢見るような表情や、軽やかで装飾的な帽子とマッチして、とても素敵な空間です。
近代化が進むパリの詩情

右 クロード・モネ「サン=ラザール駅の線路」(1877)
普仏戦争を避けてロンドンに亡命したモネは、蒸気機関車を主題にしたターナーの作品と出会い、帰国後、パリのサン=ラザール駅を主題とした作品群を制作しました。近代化が進む激動の時代を象徴するモチーフであり、都市の詩情を見出したものとして高く評価されました。
日常の輝きと各地への旅

フィンセント・ファン・ゴッホ「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」(1888), ポール・ゴーガン「白いテーブルクロス」(1886)
第2章は「日常の輝き」。後にポスト印象派と呼ばれる画家たちは、それぞれが理想とする表現を求めて新しい芸術を切り拓き、また、理想の風景を追い求めて各地へ移動。旅先や移住先で多くの作品を生み出しました。
アルルで一時共同生活を送ったゴッホとゴーガン。二人の作品が並んで展示されていました。ゴッホの作品はヴィゲラ運河にかかる橋をあざやかな色彩で描いたもの。ゴーガンの作品は、滞在していたブルターニュの下宿屋の夫人へ贈るために描かれたもので、セザンヌの影響がみられます。

中 ピエール・ボナール「地中海の庭」(1917-1918)
ひと際大きく牧歌的な作品はボナールの「地中海の庭」。大きなカンヴァスの手前にテラスが描かれていることで、テラスに立っているかのような臨場感が得られます。ミモザの花が一面に咲く“日常”の輝きに浸ることができます。
メランコリーの趣をたたえた美しい女性

ピエール・ラプラード「バラをもつ婦人」
挿絵画家としても活躍したラプラード。読書中の婦人など女性の古典的なイメージをとらえ、雅やかなモチーフを好んで描きました。
新しさを求めて。20世紀の画家たち

アンリ・マティス「襟巻の女」(1936)
第3章は「新しさを求めて」。20世紀初頭。芸術家たちは競うように新しい芸術を模索していきます。フォーヴィムスの旗手マティスは、南仏の陽光の中、独自の色彩感覚を開花させました。
他にも、 デュフィ、ブラック、ピカソなどの作品が並び、第4章「芸術の都」へと続きます。まさに甘美で全てが見どころの展覧会でした。
[ 取材・撮影・文:晴香葉子 / 2021年9月17日 ]
読者レポーター募集中!あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか?