IM
レポート
レポート
初春を祝う ― 七福うさぎがやってくる!
静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館) | 東京都
卯年生まれの岩崎小彌太の還暦を祝して制作された愛らしい御所人形が公開
七福神と童子たち、兎の冠を戴く総勢58体。布袋と弁天は小彌太と夫人かも
他にも吉祥性あふれる、さまざまな作品を紹介。国宝《曜変天目》も展示中
2
横山大観《日之出》大正~昭和時代・20世紀
吉川霊華《子の日》昭和時代・20世紀
慶入(樂家11代)《赤樂宝尽寄向付》江戸時代・文久4年(1864)
《南天蒔絵提重》江戸時代・18~19世紀
京焼《色絵松竹牡丹文壺形段重》江戸時代・18~19世紀
国宝 建窯《曜変天目》南宋時代・12~13世紀
| 会場 | 静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館) |
| 会期 |
2023年1月2日(月)〜2月4日(土)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~17:00、金曜は18:00まで。入館は閉館の30分前まで |
| 休館日 | 月曜(ただし1月2日・9日は開館)、1月10日(火) |
| 住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F |
| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル)
050-5541-8600
(ハローダイヤル)
|
| 公式サイト | https://www.seikado.or.jp/ |
| 料金 | 一般1,500円 大学・高校生1,000円 中学生以下、無料 |
| 展覧会詳細 | 「初春を祝う ―七福うさぎがやってくる!」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年12月18日
カプコンの制作世界を一望 ─ CREATIVE MUSEUM TOKYOで「大カプコン展」
2025年12月18日
トヨタが手がける没入型ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA」が横浜に誕生
2025年12月15日
古伊万里の「いきもの」80点が集合 ― 戸栗美術館「古伊万里 いきもの図会展」が1月開催
2025年12月15日
福山潤「世界観を存分に楽しんで」 ― 「アニメ天官賜福展」横浜で開幕
2025年12月14日
戦後美術史に新たな光 ─ 東京国立近代美術館で「アンチ・アクション」展
ご招待券プレゼント
学芸員募集
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!
[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]
東京都
足立区立郷土博物館「郷土博物館専門員(美術史)」の募集(会計年度任用職員)
[足立区立郷土博物館]
東京都
国立国際美術館 インターン募集中!
[国立国際美術館]
大阪府
独立行政法人国立美術館国立西洋美術館 研究補佐員(時間雇用職員)公募
[国立西洋美術館 研究資料センター]
東京都
展覧会ランキング
3
TOKYO NODE | 東京都
Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』
開催中[あと22日]
2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


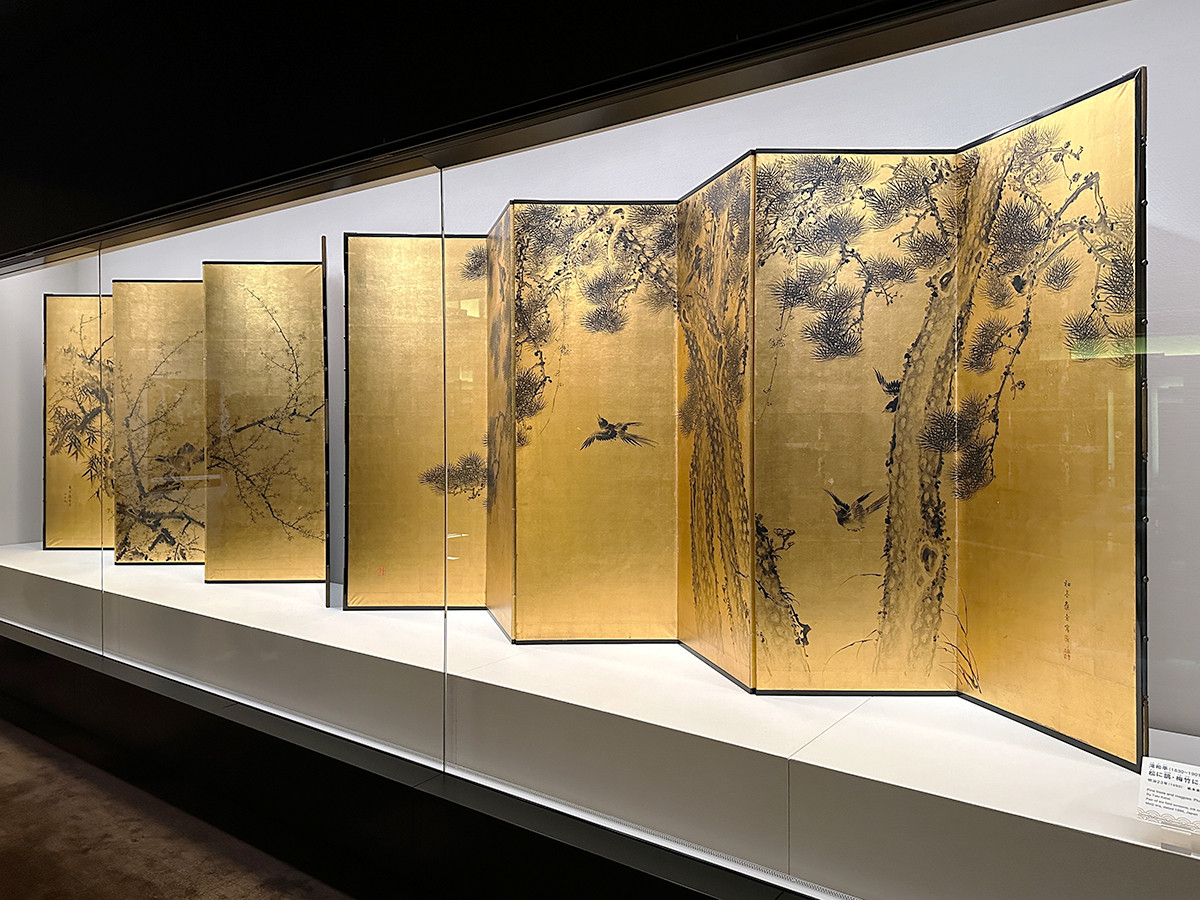





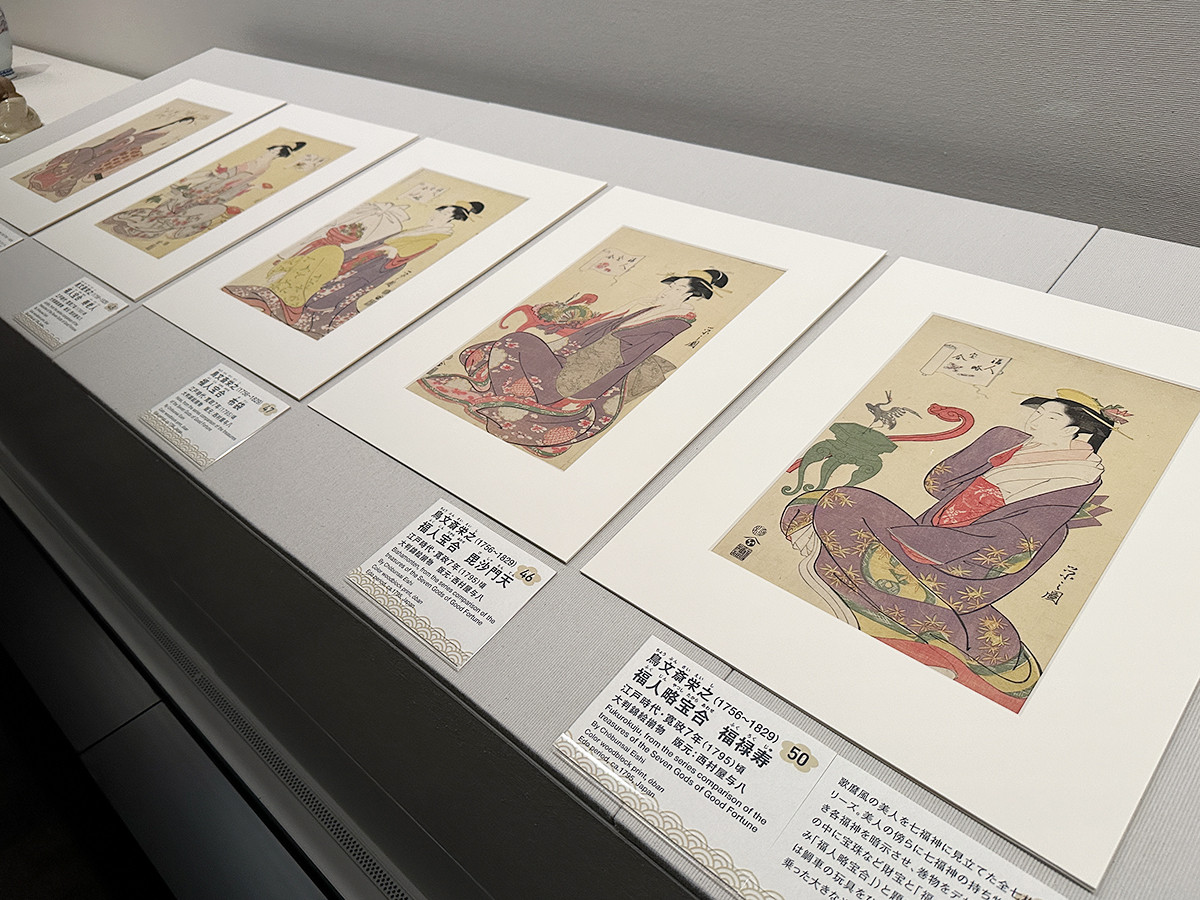

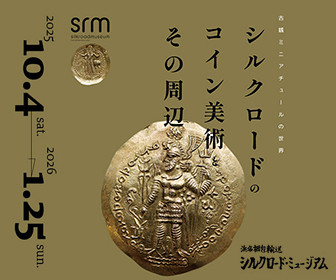
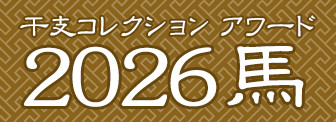

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)