IM
レポート
レポート
ひと目でわかる?昔の「えらい人」ポーズ図鑑 ― 「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」(レポート)
静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館) | 東京都
神仏や人物の“かたち”に込められた意味をやさしく解説する入門編展覧会
人物の衣装やポーズ、周囲の動物などに着目。“読みとく”楽しさを味わう
子どもにもわかりやすい解説も。夏の美術館デビューにもおすすめの企画展
2
《春日鹿曼荼羅》室町時代 15世紀[展示期間:7/5~8/11]
静嘉堂文庫美術館「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」会場
| 会場 | 静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館) |
| 会期 |
2025年7月5日(土)〜9月23日(火)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00 – 17:00 ※入館は閉館の30分前まで *毎月第4水曜日は20時まで、9月19日(金)・20日(土)は19時まで開館 |
| 休館日 | 毎週月曜日(ただし7月21日、8月11日、9月15日、22日は開館)、7月22日(火)、8月12日(火)、9月16日(火) |
| 住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F |
| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル)
050-5541-8600
(ハローダイヤル)
|
| 公式サイト | https://www.seikado.or.jp/ |
| 料金 | 一般 1500円 大高生 1000円 障がい者手帳をお持ちの方(同伴者1名〈無料〉を含む) 700円 中学生以下 無料 ※当日券の販売もございます。 ※無料チケットをお持ちの方はご予約不要です。 |
| 展覧会詳細 | 「よくわかる神仏と人物のフシギ」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2026年1月20日
装い新たに日本を読み解く、東洋文庫ミュージアムがリニューアルオープン
2026年1月19日
名刀と大名文化を紹介 ─ 特別展「百万石!加賀前田家」、東博で4月に開催
2026年1月16日
海外所蔵浮世絵が一堂に ─ 千葉市美術館で「ロックフェラー・コレクション花鳥版画展」
2026年1月16日
鹿子木孟郎の写実絵画を総覧 ― 泉屋博古館東京
ご招待券プレゼント
学芸員募集
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー)など]
東京都
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
やないづ町立斎藤清美術館地域おこし協力隊(地域アートまちづくり事業)1名募集
[やないづ町立斎藤清美術館]
福島県
春日市奴国の丘歴史資料館 学芸員(埋蔵文化財発掘調査指導員)募集
[春日市奴国の丘歴史資料館]
福岡県
茨城県近代美術館 学芸補助員(普及担当)及び展示解説員募集
[茨城県近代美術館]
茨城県
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)


![静嘉堂文庫美術館「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」会場より 住吉具慶、狩野寿石秀信《時代不同歌合画帖》江戸時代 17世紀[写真の上冊の展示は7/5~8/11。後期は下冊を展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/13/cd7515c192f8_l.jpg)
![静嘉堂文庫美術館「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」会場より 重要文化財《聖徳太子絵伝》鎌倉時代 14世紀[写真の一・二幅の展示は7/5~8/11。後期は三・四幅を展示]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/13/0ed7446dce38_l.jpg)
![静嘉堂文庫美術館「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」会場より 国宝 因陀羅筆、楚石梵琦題詩《禅機図断簡 智常禅師図》元時代 14世紀[展示期間:7/5~8/11]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/13/5bc11a268b6b_l.jpg)

![静嘉堂文庫美術館「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」会場より 狩野探幽《二十八祖像》江戸時代 17世紀[展示期間:7/5~8/11]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/13/1b90bbef77d8_l.jpg)
![静嘉堂文庫美術館「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」会場より 狩野常信《琴棋書画図屏風》江戸時代 17~18世紀[展示期間:7/5~8/11]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/13/51a9736e1cc6_l.jpg)
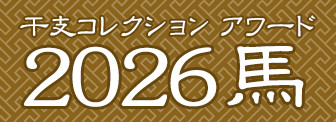

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)