読者
レポート
レポート
兵庫県立美術館「不思議の国のアリス展 神戸展」
兵庫県立美術館 | 兵庫県
| 会場 | 兵庫県立美術館 |
| 会期 |
2019年3月16日(土)〜5月26日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~18:00 (特別展開催中の金曜日と土曜日は20:00まで) ※入場は閉館の30分前まで |
| 休館日 | 月曜日(ただし、4月29日、5月6日は開館)、5月7日(火) |
| 住所 | 〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1 (HAT神戸内) |
| 電話 | 078-262-1011 |
| 公式サイト | http://www.alice2019-20.jp/ |
| 料金 | 一般 1,400(1,200)円 / 高校・大学生 1,000(800)円 / 小・中学生 600(400)円 ※( )内は前売券および20名以上の団体料金 ※小学生未満無料。金額はすべて税込み。 ※障がい者手帳をお持ちの方は、本人と介添えの方1名まで当日料金の半額。他の割引とは併用できません。 ※当日券と前売券は、ローソンチケット(Lコード53878)、チケットぴあ(Pコード992-018)、セブンチケット、CNプレイガイド、阪神プレイガイド、チケットポートほかにて販売。 ※当日券の販売期間は2019年3月16日(土)~5月26日(日)、前売券の販売期間は2019年1月19日(土)~3月15日(金) 【特別先行前売券】※HARD ROCK CAFE ピンズ付き前売券 一般 3,200円 / 高校・大学生 2,800円 / 小・中学生 2,400円 ※特別先行前売券は、2018年12月15日(土)~2019年3月15日(金)の期間に、ローソンチケット(Lコード:53878)で販売。 |
| 展覧会詳細 | 「「不思議の国のアリス展」神戸展」 詳細情報 |
0
兵庫県
2019年3月16日(土)〜5月26日(日)
兵庫県立美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
福岡県
2019年12月3日(火)〜2020年1月19日(日)
福岡市美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
静岡県
2020年2月1日(土)〜3月29日(日)
静岡市美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
新潟県
2020年6月27日(土)〜9月6日(日)
新潟市新津美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
おすすめレポート
ニュース
2026年1月10日
創業からの歩みをたどる多彩な展示 ― 高島屋史料館「タカシマヤ クロニクル」展が開幕
2026年1月10日
SOMPO美術館、開館50周年で式典 ― 新宿の文化発信、次の半世紀へ
2026年1月9日
怒りと守護のかたち ─ 静嘉堂文庫美術館で「たたかう仏像」展が開催中
2026年1月9日
新宿からたどる日本近代美術 ― SOMPO美術館「モダンアートの街・新宿」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
歴史的建造物と庭園で働きたい方を募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
【豊島区】学芸業務調査員募集
[郷土資料館、雑司が谷旧宣教師館、鈴木信太郎記念館、豊島区役所のいずれかの予定です。]
東京都
国士舘史資料室 準職員(有期限職員)の募集
[国士舘史資料室]
東京都
【豊島区】学芸研究員募集
[豊島区立郷土資料館、雑司が谷旧宣教師館、鈴木信太郎記念館、豊島区役所のいずれか]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)
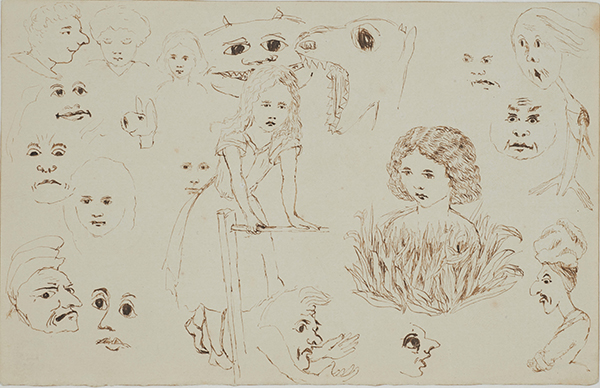
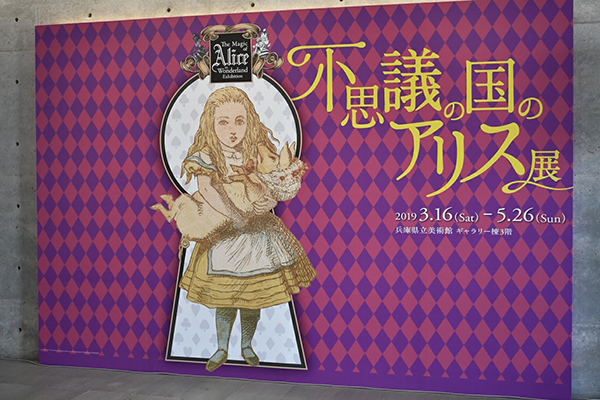
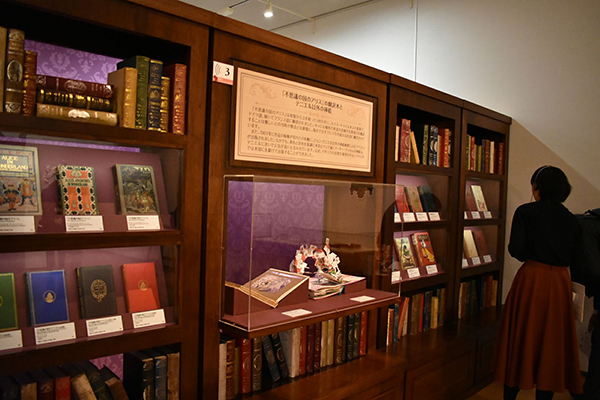





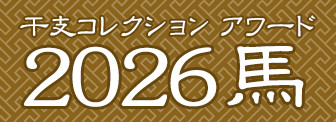

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)